(2ページ目です)
アンガーマネジメント|イライラしない会話術その2.「私」を主語にする
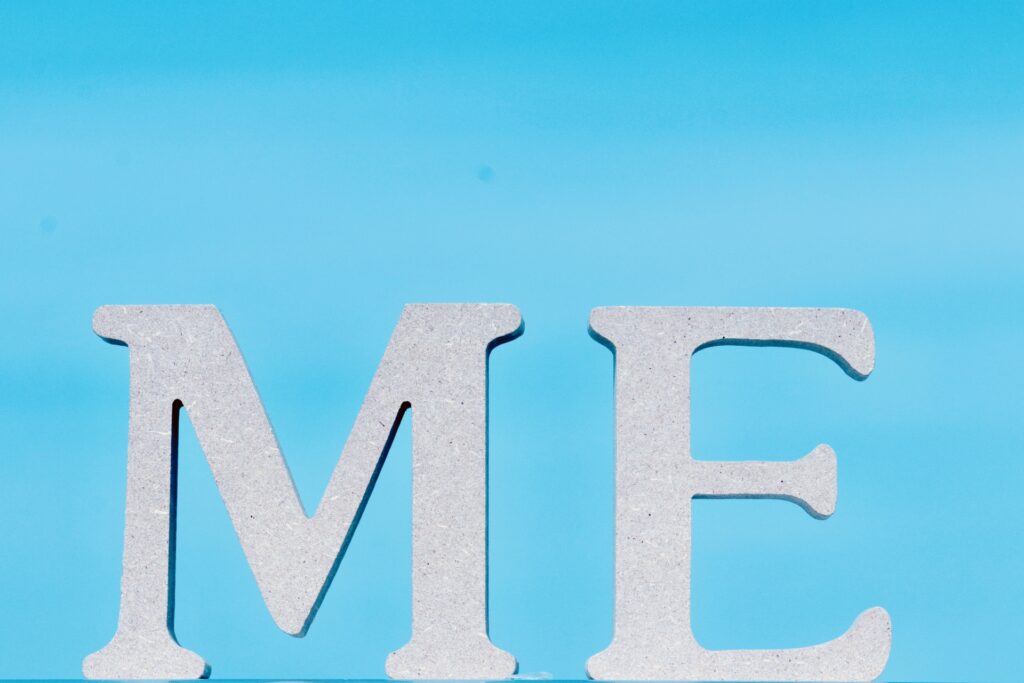
「べき論」を振りかざすのではなく、自分の欲求を明確にして伝える、ということをこれまで学んできたので言うまでもありませんが、主語は「私」にして伝えると効果的です。
英語で言うなら「you should」ではなく「I want」です。
先程の例でも、欲求を「I want」の形で伝えています。
こうすれば「べき論」を振りかざすことによる反感を買わずに、欲求がシンプルに伝わります。
アンガーマネジメント|イライラしない会話術その3.過去を持ち出さない

「また勉強せずにゲームばっかりして」「いつも勉強せずに遊び呆けてる」
親子の間で聞こえてきそうなこんな会話ですが、過去を持ち出すのは利口なコミュニケーションとは言えません。
「いや、この前は勉強したじゃん」「帰ってくる30分前までは3時間位勉強したよ」
などと反感を買いかねません。
そもそも「いつも言っているじゃないか」という言葉の裏には、「言うだけで、伝わっていない」ということになります。
つまり上手なコミュニケーションが取れていないことになります。
いちいち過去を持ち出さずに、忍耐強く「その都度正しいコミュニケーションのとり方で、行動是正する」という姿勢を保ち続ける必要があります。
もちろん、1回で伝わる人、5回言わないと伝わらない人、10回言っても伝わらない人もいますが、いつかは伝わります。
30回言って初めて伝わる場合もあることを考えると、毎回イライラしていたらキリがありません。
過去を持ち出さず、今の話をしましょう。
アンガーマネジメント|イライラしない会話術その4.明確な表現を使う

何故「この前も言ったじゃないか!」というに至る「伝わらないコミュニケーション」になってしまうのでしょうか?
理由は一つではありません。
しかし主要な要因は、明確な表現を使えていない、という点ではないでしょうか?
など、明確なコミュニケーションが出来ておらず、「伝わるだろう」と相手に甘えたコミュニケーションになっています。
繰り返しになりますが、「相手の反応が、あなたのコミュニケーションの成果である」という言葉を脳裏に刻み込んでおくと、少なくともイライラにはなりませんし、より明確で伝わるコミュニケーションを取ろうという意識に繋がります。
といったように、リクエストするときの6W4Hを明確にすると良いでしょう。
たまに、「普通分かるだろ・・・」「考えたら分かるだろう・・・」という人がいます。
しかし、十人十色、考えて分かることは人それぞれ違います。
「考えたら分かるだろう・・・」とバカにしているその相手が考えて分かること全て、あなたは考えて分かるんですか?
そんなハズはありません。
その人が考えて分かること100個の内、あなたがどれだけ知恵を振り絞って考えてもわからないことが、5個や10個や20個あるはずです。
この事実を脳裏に刻んでおけば、「普通分かるだろ・・・」「考えたら分かるだろう・・・」という考え方から、「どうすれば伝わるかな?」と性格で明確なコミュニケーションを取ろうとする姿勢に必然的に変わるはずです。
アンガーマネジメント|イライラしない会話術その5.ゆっくり話す

メラビアンの法則は有名で良く話の流れで引き合いに出されます。
伝わる情報の内、視覚情報55%、聴覚情報は38%、言葉は7%というやつです。
しかしこれは本来のメラビアンの実験から導き出される原理ではありません。
本来の原理は次のようなものです。
例えば、「あなたが大好きです」(言葉)とにらみ顔で(視覚)言うと、視覚であるにらみ顔を優先され、「あなたが大好きです」という言葉は相手に伝わらないということです。
とっても嬉しそうな声のトーンと口調で(聴覚情報)、「あなたに会えて全然嬉しくない」と言っても、「嬉しいんだな」と伝わります。
このように、本来のメラビアンの実験から導き出されることは、「言語情報(言葉)と非言語情報(視覚情報・聴覚情報)は揃えましょう」ということです。
つまり叱ったり、行動是正するときに、睨んだり、威圧的な雰囲気を出したり、声を荒げるのではなく、ゆっくり話し、そして落ち着いた穏やかな表情で話をしましょう、ということです。
実際、クライアントのゴール実現を後押しする、単価100万円を超える我々のようなコーチは、言語よりも非言語の方に圧倒的な情報をのせていきます。
言葉よりも文字通り何倍も非言語情報を相手はキャッチするからです。
ですので、自分が話をするときの口調や表情など、非言語情報を揃えましょう。
因みにこのゆっくり話すというのはもう一つメリットがあります。
以前の記事で、明るいフィジオロジーを徹底すると解説しました。
そしてフィジオロジー(表情や声のトーンなど)を明るくすると、イライラも収まり、予防にも繋がると説明しました。
そしてこの「ゆっくり話す」はまさにこれと同じ効果があります。
人は起こっているときのほうが早口になる傾向があります。
そこであえてゆっくり話すことでイライラを抑えることができるということです。
アンガーマネジメント|イライラしない会話術その6.一貫性を持つ
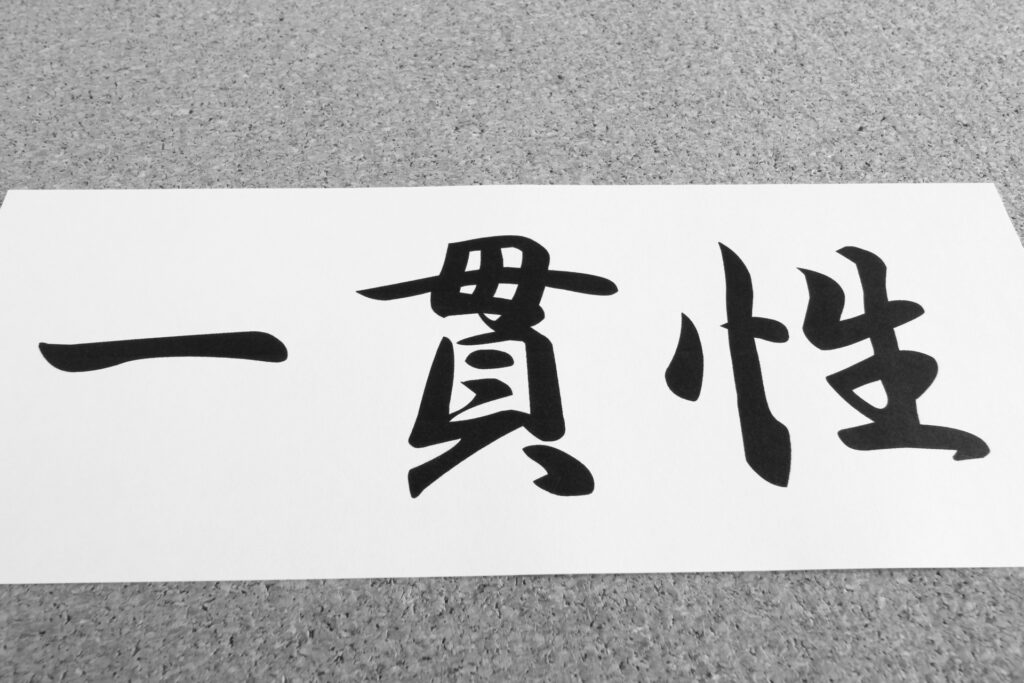
その時の気分によって、「昨日は怒らなかったことに対して今日は怒っている」「Aさんのときは笑って見過ごすけど、Bさんのときは怒っている」など、態度を変える人がいます。
要はルールや基準がブレブレで一貫性がない人です。
このように、一貫性がない人は信頼されません。
そして「今は機嫌が悪いから、いわれのないようなことでもいきなり怒り出すかもしれない」と安心できません。
そして距離を置かれてしまいます。
そしていざ怒ったときのルールがどれだけ正当なものであろうと、そのルールに反したときの対応を機嫌次第で変える人はやはり信頼されません。
そのため、一貫性を持つというのはコミュニケーションを通じて信頼関係を構築していく上で非常に大事です。
まとめ
以上、本記事ではアンガーマネジメントの見地から、適切な会話をする方法を6つご紹介しました。
振り返ると下記6点です。
但し、これらの本質は下記の2点です。
そのため、この2つの本質さえクリアできれば、上記6点のみにとらわれる必要はありません。
ご自分なりに効果的な方法を模索していただいても構いません。
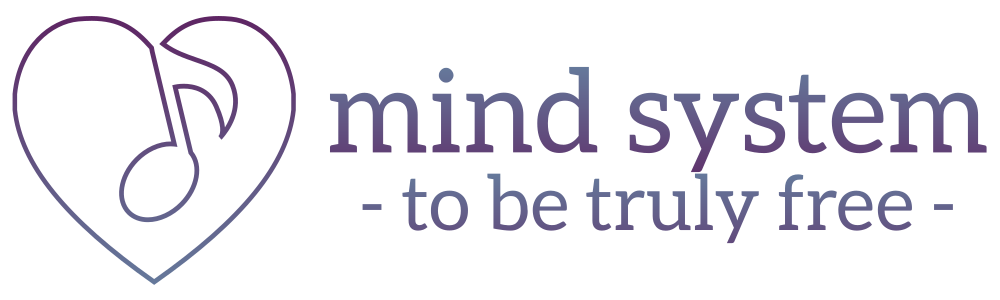

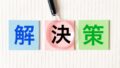
コメント